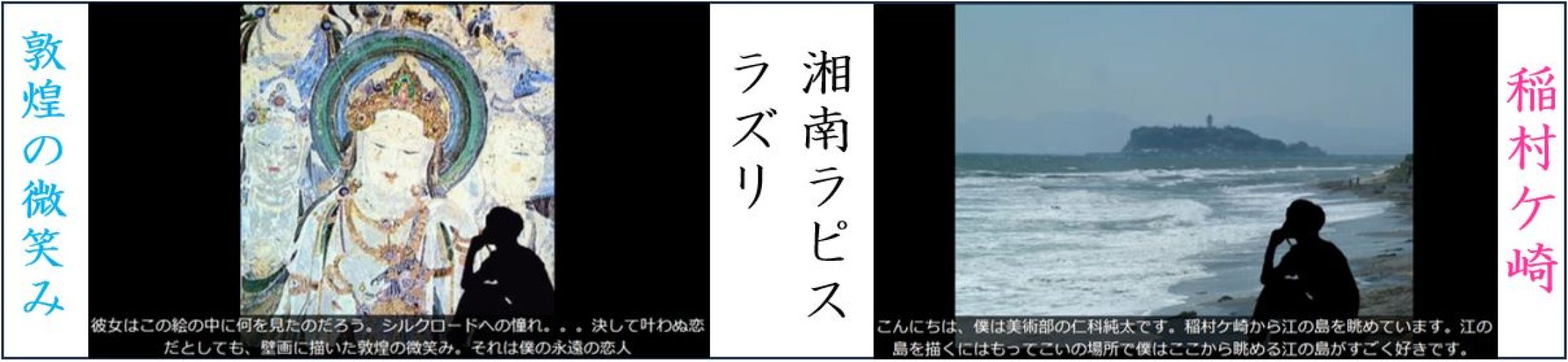第1章 プロローグ
有紀は札幌三越のデパ地下で十五分も並んでようやく買った大好きなスィートポテトを携えて地下街のポールタウンを歩いていた。一個つまんでみようと袋を空けた。
「あら有紀じゃない。久しぶりね。元気だった?」と声を掛けて近寄ってきた女性がいた。大学時代に同じサークルで同期だった和子だった。その後ろには小学生ぐらいの女の子と男の子が二人寄り添っていた。
「本当久しぶりね。こんな所で会うなんて奇遇ね。和子も元気そうね。いやぁ、めんこいね。子供も二人もいて賑やかそうだね」
「賑やか所の話しでないよ。もう家の中はすっちゃか、めっちゃかでなまら大変なのさ」という和子の言葉とは裏腹に子供を見る瞳は優しかった。
有紀は「そういえば、サークルの同期会の案内が来てたね。確か来週だったよね。もちろん和子も来るっしょ?」と尋ねた。
和子は「私はちょっと行けないんだわ。みんなに宜しく行っておいて」と言いながら、有紀は私が行けないのを知っているのにわざと意地悪して言っているんだと思った。和子は今の旦那と結婚する前に同じサークルの西嶋真之と付き合っていた。別れた切っ掛けは彼の渡米だった。医薬に関する学位論文が認められて米国の大学に研究員としていく事になった。彼は和子にプロポーズして一緒に米国に着いてくるように頼んだが和子は葛藤した。海外に行けば研究熱心な彼は大学に籠もりっきりになって仕事に没頭するのは予想が付いた。もし二人で渡米すれば言葉の通じない社会の中で自分だけが部屋の中で一人っきりになってしまう。愛してはいたがその寂しさに自分は耐えられないと思い、悩んだ末にプロポーズを断り二人の関係はそれで終わった。知人には和子は冷たいと言われた。よく北海道の女は別れに対してドライだといわれるが仕方がない。それが現実なのだ。後腐れなんか気にしていたら恋愛なんて出来やしない。どうせ別れるなら北海道の澄んだ空のように早めに綺麗さっぱり別れた方がいい。言う奴には勝手に言わせておけばいい。分かりきった不幸を背負って生きて行くなんて「はんかくさいっしょや」と言い返してあげる。彼との別離から既に十年近くの歳月が経っていた。彼が数年ほど前から日本に戻っていた事は知っていた。札幌の国立大学に新設された先端医薬研究所の主任研究員として米国から招聘された。その特集記事が地元の北海道新報に掲載されていた。今回の同期会は彼の友人が幹事となって開催するので日本に帰ってきた真之の歓迎会的な意味合いもある。そんな同期会に和子が行けるはずもない。サークルの同期だった有紀なら二人の事情も十二分に承知しているはずだ。そう言えば学生の頃から彼女は時々、変な言い掛かりを付けたり遠くから挑みかかるような視線で見つめていた気がする。
小学四年生になる長女の由美子が「ママ早く。スイートポテトが売り切れちゃうよ」と和子の左手を引っ張った。
「そうだよ、早くしてよ。ママの立ち話は長いんだもん」と小学二年生になる長男の幸明も姉の真似をして右手を引っ張った。
「はいはい。分かったから。したらね有紀。そういえば、あなた子供はまだなの?」
「うん、ちょっと事情があってね…」と有紀は言い淀んだ。
和子は「あんたも、もう三十路過ぎてるんだから早く作りなさいよ。子供は良いもんだよ。したらね」と言って子供と両手をつないで有紀と別れた。
有紀は和子の後ろ姿を羨望と憎悪の入り混じった感情で眺めた。結婚して五年たったが子供は出来なかった。夫婦仲は悪いわけではないし人並みに夫婦の営みもある。しかし子供がなかなか授からなかったので今も不妊治療をしている。楽しそうに子供と手を繋いでいる和子の後ろ姿を睨んでいると悔しくて涙が出そうになった。「子供が授からなくて悩んでいるのを知っていて意地悪してあんな事を言ったんだわ」と思った。そう言えば今年の年賀状にもデカデカと子供と一緒に写った幸せそうな写真を載せて、「あなたも早く作れば」なんて書いてあった。それに学生の時だって…和子さえいなければ真之と付き合っていたのは私だったのに…和子の存在が自分の幸せを奪っていく女のように思えて激しく嫉妬した。涙を滲ませながらすすきの駅へと続く地下街を走り抜け階段を駆け上がった。川の流れのように行き交う人の流れを抜け出して一刻も早く誰もいない所に逃げ込んで大声で泣きたかった。
第2章 ライラックの大通公園
和子は三越のデパ地下でスィートポテトを買ってから地下通路のポールタウンを歩いて大通駅から地上に出た。札幌はライラックの季節だった。紫色のライラックを見て北国にもようやく初夏が来たと実感した。脳裏に数年前に他界した母の面影が過ぎった。母は北星学園高校の卒業生で学園内のライラックの美しさを話し聞かせてくれたものだった。
ライラックは札幌市の市の花に指定されていて市民のみならず観光客にも愛されている。北星学園の創始者であるサラ・クララ・スミス女史が故郷である米国のニューヨーク州から苗を持ち帰って校庭に植えたのが札幌のライラックの始まりとされている。明治の開拓時代に来日したサラ・クララ・スミス女史は当時、札幌農学校で教鞭を取っていた新渡戸稲造たちの協力を受けながら女学校を設立した。これが札幌の女子中等教育の魁と言われている。ちなみに北星学園の名付け親は新渡戸稲造でShine like stars, in a dark world.(暗い夜空の星の如く光り輝く人となれ)が学園名の由来となっている。そんな縁もあって母は五千円札の肖像画に新渡戸稲造が選ばれた時にも誇らしげに母校を語っていた。
新緑に満たされた大通公園で人々はベンチに座ったり芝生に寝そべったりしながらライラックを眺めていた。子供たちと芝生に座り買ってきたスィートポテトを食べた。
スィートポテトをペロリと食べた息子の幸明が「ママ、とうきびも食べたいよ」とせがんだ。
「したって、あんたスィートポテト食ったばっかりっしょや」
「そりゃ美味しかったけど、こんな小っこいんだもん。直ぐ腹減っちゃうっしょや。ねぇねぇママ、とうきび食べたいよう」と幸明は地団太を踏んだ。
和子は「全く仕方ない子だねぇ、あんたは」と焼きたてのとうきびを買ってから子供たちと散歩した。巨大な噴水のある一角に特設ステージが設けられていてピエロの格好をした大道芸人がマジックをしていた。
幸明は立ち止まってそのマジックを眺めた。巨大な剣を飲み込んだり、飲み込んだはずのボールが口から出てきた。幸明は「姉ちゃん、凄いね、凄いね」と大興奮してはしゃいでいたが姉の由美子は冷静だった。
「あんた馬鹿だね。マジックなんだから、カラクリがあるに決まってるっしょ。もっと大人になりなさいよ」とませた事を言った。
「したって僕、子供だもん。大人になんかなれないよ」
「馬鹿ねぇ例え話っしょや。あんたが大人になるなんて十年早いんだわ」
「僕は七歳だからあと十年経っても十七だがらまだ大人になれないよ」と得意気に反論した。
「いちいち口ごたえして、あんた最近生意気なのよ」と頭を軽く小突いた。幸明は泣きながら母の足に縋った。「こら由美子。なに泣かせてるの。あんたお姉ちゃんなんだから、いじめてないで仲良くしなきゃ駄目っしょ」と叱られた由美子はシュンとして俯いた。幸明は母の後ろに隠れながら姉を見てあっかんべーをした。
「幸明め。家に帰ったら覚えてろよ」と思いながらほっぺを膨らませて弟を睨みつけた。
第3章 札幌ゲノメディカ
西嶋真之は大学の研究所で修士過程一年目の市河慶二と修士論文のテーマや研究者としての心構えについて話をしていた。普通、修士の研究テーマは担当教官レベルで話が付くのだが敢えて一人一人の学生と面談する機会を設けていた。研究者としてのスタートは修士課程だ。最初に確固たる方向性と覚悟を持たせる事が大切だという信念を持っていた。しっかりとしたスタートを切ることによって、その学生の研究者として素質を伸ばして数年後には研究室を引っ張っていく人材になって欲しいと願っていた。
さらに市河に関して心配な事があった。彼を指導している博士課程の学生から彼が最近ススキノの夜遊びに夢中になって研究に身が入っていないという相談を受けていた。以前は学生のプライバシーには踏み込まず自己管理に任せていた。しかし数年前に苦い経験をした。
当時、速見卓巳という優秀な学生がいたが、ある時期からススキノの夜遊びにはまってしまった。直ぐに飽きるだろうとたかをくくっていたが徐々にのめり込み単なる夜遊びから危ない仕事に手を出し、大金を手にして博士課程の途中で退学し研究の場から去った。
数週間前にその速見から就職先を紹介してくれと電話があった。しかし真之は断った。その前にも2回ほど医薬業界のコネを使って就職を斡旋したのだが一ヶ月も持たないで辞めてしまった。また直ぐに辞められては紹介した自分の信用も下がるし紹介された方もたまったものではない。速見の優秀さを知っているだけに早い段階で夜遊びをやめさせていれば彼が人生を狂わせる事がなかったのにと後悔している。
速見の二の舞にならないように、市河にはススキノの夜遊びを止めて研究に集中するように厳しくお灸をすえた後、セイタカアワダチソウという植物の天然毒を遺伝子に組み込んだマウスの遺伝子研究について話をした。近年、このセイタカアワダチソウという米国原産の外来植物が北の大地にも進出してきている。研究所の窓から見える大学の農場にも生えていて夏の終わりから秋に掛けて黄色い花を付ける。
本州では既に戦後から猛威をふるっている植物で特に関西や北九州に多い。元々鑑賞用として庭に植えられていたのが野に逃げ出した植物だけに鮮やかな黄色い花は美しい。夏の終わりにはススキと争って生い茂り空き地や原野で黄色い花房が秋風に揺られている。河川改修や埋め立て地などの広大な土地を黄色い絨毯に変えるその生命力は他の植物を圧倒している。戦後の日本社会が米国化して行ったのと時を同じくして米国原産の植物が日本古来の植物を駆逐して広がって行ったのは何とも皮肉な結果である。
セイタカアワダチソウは自らの根から天然毒を出して競争相手の植物の成長を阻害する。専門用語ではアレロパシー(他感作用)と呼ばれている作用だ。この天然毒はシス・デヒドロ・マトリカリア・エステルという長ったらしい名前の物質で、これを遺伝子に組み込んだマウスを使って様々な病気への耐性を調べるというのが市河の研究テーマだった。
真之は札幌に戻ってくる数年前まで米国のシアトルにあるノーベル生理学・医学賞を何人も輩出している有名な大学で医薬の研究をしていた。キャンパスの敷地は広大で地図なしでは迷ってしまうほどの広さだった。北海道大学も広いがその一倍半ぐらいの面積があった。初めてそのキャンパスに足を踏み入れた時はさすがは広大な国土を有する米国の大学だと感心した。
研究室では毎日時間が過ぎるのも忘れて研究と勉学に打ち込んだ。渡米前にプロポーズを断られた傷心を忘れようと日本にいた時よりも研究に没頭した。やがて権威ある論文誌にも数多くの論文を発表して一人前の研究者として認められた。得意とする分野は天然毒と遺伝子の研究だった。一見畑違いのように思える二つの分野を切り口として独創的な研究を行い新薬の開発をした事が大きく評価された。
米国の大学でも引く手あまただったが母校の大学に新設された先端医薬研究所の統括研究員として誘われ戻ってくる事に決めた。役職的には所長に次ぐNo2だ。所長は対外折衝の仕事が多いので実質的に研究を指揮する副所長のポストだ。三十代後半という年齢からすれば、異例の大抜擢だった。
札幌に戻ってくる際、条件として大学に認めてもらったのは創薬ベンチャー企業の社長も兼任するという事だった。それが譲れない条件だった。米国で研究していて肌で感じた事は大学とベンチャー企業には密接な関わりがあるという事だった。それは織物の縦糸と横糸の関係に似ている。両方が互いに絡み合い医薬産業という名の西陣織が色鮮やかに織らていくのである。
現状のままでは日本の医薬業界は目まぐるしく発展する米国に飲み込まれてしまうという危機感を抱いていた。米国で研究をすればするほど焦りは大きくなっていた。研究者としては米国の方が資金も環境も恵まれていた。現に最近の生理学・医学分野のノーベル賞受賞者には、ほぼ毎年米国人が選ばれている。そのまま残って研究を続けていれば良い仕事が出来るし研究者としての名声も高まるだろう。しかし札幌に戻る事を決意した。このままでは日本の医薬界は駄目になる。俺が日本を変えなければという強い使命感が自分を動かした。
帰国後、優秀な若手研究者を日本中から募り創薬ベンチャー企業を立ち上げた。会社名は「札幌ゲノメディカ」。「ゲノム」と「メディカル」を繋げた造語だ。産学協同という母校からのバックアップもあり資金も施設も満足いくものが得られた。真之には大きな野望があった。札幌を世界の創薬産業のメッカにする事だった。ベンチャーの創設はその第一歩だ。先端医薬研究所で新薬の種を見つけて「札幌ゲノメディカ」と共同で研究し創薬開発を垂直立ち上げするのが狙いだった。
さらに特許や許認可に関する特許部も強化して米国に負けない万全の体制を整えた。早くもその成果が出始めていた。将来、巨万の富を生む可能性がある新薬を開発して特許を出願した。しかし他社から特許の棄却請求が出て現在裁判で係争中だった。
相手は日本の中堅製薬会社の三ツ橋製薬だった。こちらが出願する数日前に全く同じような特許を出願していた。三ツ橋製薬の出願内容に目を通してやられたと思った。サンプルやデータの結果がこちらと瓜二つだった。新薬の構造解析まで全く同じだったので盗用されたと直感した。しかしそれを証明する手立ては何もなかった。大学とベンチャー企業で織り成した最初の研究が華々しい成果を上げることが出来たと喜んでいたのも束の間まさかの大転落だった。創薬ベンチャーは特許を押さえることが出来なければ一文の価値もない。特許を抑えて独占販売するか特許のライセンス料を取るしか利益を挙げる方法はない。そこが多種多様な医薬を大量生産する工場を持つ製薬会社とは違う。特許が取れなければ、それまでに積み重ねて来た研究は単なる無駄金の消費でしかない。日本の創薬産業の風雲児になるべく札幌に来たというのに日本の製薬会社に潰されるとは思っても見なかった。
しかし、やられてばかりはいられない。絶対に犯罪行為を許す訳にはいかない。特許弁護士や弁理士と共に法廷闘争の手続きを整えた。更に敵側に秘密裏に内偵をおくり証拠探しを進めている。目には目を歯に歯をの戦略だ。
第4章 同窓会
真之はその夜、大学時代のサークルの同窓会があったので仕事を切り上げて帰り支度を始めた。大学近くの北十八条駅まで歩きそこから地下鉄に乗り、すすきの駅で降りて大学時代によく飲んでいた居酒屋の「つぼ八」に向かった。時々、学生たちと飲みには行くが大学周辺の安い居酒屋が定番だった。
煌びやかねネオンの氾濫する歓楽街を歩くのは久しぶりだった。ネオンが目に眩しかった。札幌での生活は大学とベンチャーを行き来して時々、家に帰るという研究漬けの生活だった。実家に居候を決め込んでいるので家でする事は風呂と飯と睡眠ぐらいのものだ。社会的には先端医薬研究所のNo2という肩書きを持ってはいるが実家では、ぐうだら息子だった。
両親も四十路前の独身男の息子には複雑な心境だろう。恐らく内心では新薬の開発ばっかりしてないで嫁の開発もしろと思っているのは間違いない。時々、母親には嫌味を言われることもあるが実家にいると掃除、洗濯、食事と何でもやってもらえて研究活動に集中できる。楽なのでつい甘えてしまっている。
十年前に和子と別れてからも何人かの女性とは付き合ったし、今も恋人はいるが最後の一歩を踏み出す気にはなれなかった。「つぼ八」の暖簾の前に立った。社会人になったのだで、もっと高級な店でも良いんじゃないかと思ったが、いざ店内に入ってみると学生に戻ったような懐かしい気分がした。和子が来ているかも知れないという淡い期待を抱きつつ席に向かった。留学中は彼女への思い出を掻き消すようにして研究に没頭していた。だが和子を心の奥底へ押し込めようとすればするほど思い出してしまった。十年の月日が流れていたが心に住んでいる和子はあの当時のままだった。未練がましいとも思うが自分ではどうしようもなかった。
風の噂では渡米してから他の男と結婚して今では子供も二人いるという。今や自分は社会的に見れば羨望の的に値する成功者だ。あの時の渡米は間違いではなかった。そう自信を持って言える。その事を和子に誇りたかったし、それを彼女に認めて欲しかった。本心を言えばプロポーズを断り一緒に来なかった事を後悔していて欲しかった。「過去に戻れるならあなたと一緒になれば良かった」と言う言葉を和子から聞くことができたらどんなに救われるだろう。
テーブルに座っている面々を眺めたが和子はいなかった。「今さら会ってどうするものでもないし。馬鹿だな自分は」と自嘲しながら友人たちと昔話に花を咲かせた。久しぶりに会った友人はみな歳相応の風貌になっていたが、気心の知れた、ふるき良き友たちと酌み交わす酒は上手かったので、ついつい学生の頃を思い出して酒が進んだ。
宴もたけなわで盛り上がっている中で女友達から耳を疑うような話を聞いた。渡米した直後、既に和子が妊娠していたというのだ。自分が渡米してから十ヶ月も経たない内に子供を生んだのでサークル仲間ではちょっとした噂になったそうだ。渡米後、他の男と結婚して子供を生んだという話は聞いたがまさか出産がそれほど早かったのは知らなかった。別れたのは三月だった。そして娘を産んだのが十一月上旬という事だった。妊娠期間を十月十日として指折り数えてみると妊娠したのは自分と別れる前の一月という事になる。
思い返せば別れる直前まで肉体関係はあった。避妊具も毎回付けていた訳ではなかった気がする。若しかして産んだのは自分の子供かも知れない…しかも他の男と結婚してから出産した。何故自分に相談してくれなかったのだ…と激しい眩暈を覚えた。一次会が終わった後、二次会へ移動する途中に幹事の中村からこっそりと和子の現住所と電話番号を教えてもらった。結婚で苗字が桜井から清田に変わっていた。住所は札幌市西区の発寒だった。
第5章 元カノの家
真之のベンチャーは札幌市の郊外、北区の百合が原公園の近くにあった。札幌駅から北へ7キロほどで公園の傍には丘珠空港がある。主に北海道内の路線を結ぶ空港で会社の窓からは上空を旋回する飛行機が良く見えた。
同窓会で和子の噂を聞いて以来、気になって仕事が上の空になってしまった。思い切って自宅を訪ねてみることにした。会社から車を飛ばして和子の住む市発寒へと向かった。近くのコンビ二に車を停めてからサングラスを掛けて探し歩いた。
表札に【清田文忠・和子・由美子・幸明】と刻まれた一軒家を見つけた。家の中には誰もいないようだった。この家で和子と自分の娘かも知れない娘が暮らしている。そう思うと妙に自分だけが除け者にされているような寂しい気分になった。
暫くすると学校帰りの子供たちの声が聞こえてきた。怪しまれないように家から少し離れて様子を窺った。手を繋いで仲の良さそうな姉と弟がランドセルを背負って帰ってきた。その女の子を見て和子の娘だと直感した。目の感じやシャープな顎の形がそっくりだ。すらっと伸びた高い鼻や大きな口はどことなく自分に似ていると思った。
二人の子供は門を開けて中に入っていった。真之は女の子の髪の毛を手に入れてDNA鑑定すれば自分の娘かどうかがはっきりする。コンビニに停めてあった車に戻ってからスムーズに髪の毛を手に入れる妙案がないものかと考えた。